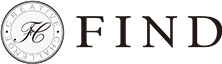COLUMNコラム
- 2025.09.04
- その他
スマートハウスとは?代表的な3つの設備、メリット・デメリットを解説
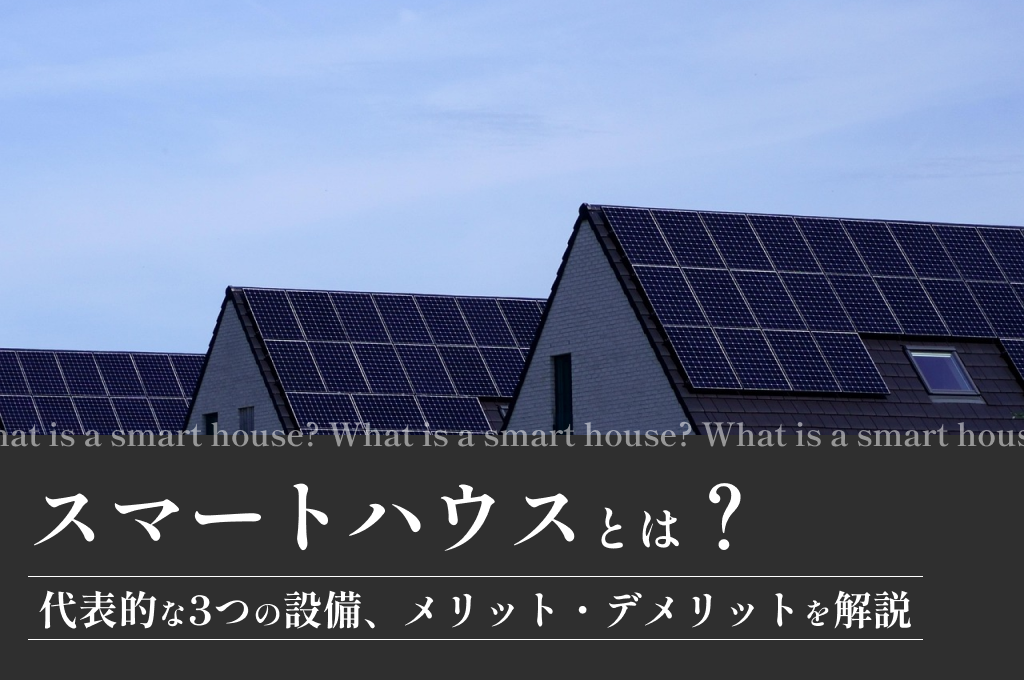
「スマートハウスってどんな家のことをいうの?」
「スマートハウスにするメリットやデメリットは?」
このような疑問やお悩みをお持ちではありませんか?
スマートハウスは自宅での発電や蓄電、エネルギーの最適管理を通じて暮らしの自立性を高め、省エネや安心感を提供する住宅です。
そこで本記事では、スマートハウスの説明や代表的な3つの設備、さらにメリット・デメリットについて解説します。
エネルギー価格の高騰や自然災害の増加が続く今、電力の自給自足と節電を可能とするスマートハウスに関心があるという方はぜひご覧ください。
目次
1.スマートハウスとは?

スマートハウスとは、エネルギー効率や環境への配慮を重視し、家庭内でのエネルギーを最適に活用できるよう設計された住宅のことを指します。
この概念が提唱され始めたのは1980年代のアメリカで、当初は家電や住宅設備を一元管理して生活の快適性を高めることが目的でした。
現在では、創エネ・蓄エネ・省エネのシステムを備えたエネルギー自立型の住宅として認識されることが一般的です。
後ほど詳しく説明しますが、スマートハウスには、次の3つの設備の導入が必要です。
| 【スマートハウスに必須の3設備】 ・太陽光発電システム ・家庭用蓄電池(電気自動車含む) ・HEMS(ヘムス/Home Energy Management System) |
(1)スマートホームとの違い
スマートハウスとスマートホームは似た言葉ではありますが、特徴や目指す方向性が異なります。
スマートハウスは節電・省エネ・防災の観点からIT技術を利用した住宅を主に指す言葉ですが、スマートホームはIT技術を取り入れた便利で快適な生活を送るという「暮らしやすさ」「快適な住まいにすること」など状態を指すという違いがあります。
| スマートホーム | スマートハウス | |
| 意味 | ネット接続された家電・設備で適な住空間を作ること | 節電・省エネ・防災に必要な設備を備えた住宅そのもの |
| 目的 | 家電や設備のIoTによる利便性・快適性・防犯性の向上 | ・エネルギーの自給自足による自立 ・エネルギー利用の効率化 ・節電・光熱費の削減 |
| 特徴 | ・家電や設備のネットワーク接続 ・スマートホーム製品導入の導入 | ・電気を自宅で「作る」「貯める」「効率よく利用する」を実現 ・非常時にも安心 |
スマートホームについてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
スマートホームとはどんな家?メリット・デメリットと主な設備・家電を解説
(2)IoT住宅との違い
IoT(Internet of things)住宅とは、家庭内の設備や家電をインターネットとつなぐことで快適に過ごせる住宅のことです。
近年スマートハウスとIoT住宅は融合しつつあり、エネルギー効率の最適化に加えてIoTも兼ね備えたより高度な住宅がスマートハウスとして位置づけられるように。
その結果、スマートハウスは「非常時にも安心して住める省エネ住宅」にとどまらず、利便性・快適性・防犯性など暮らしの質をトータルに高める住宅として注目されています。
2.スマートハウスの代表的な3つの設備

創エネ・蓄エネ・省エネによって家のエネルギー効率の最適化を図るスマートハウスには、次の3つの設備の導入が必要です。
| 【スマートハウスの基本3設備】 ・創エネ:太陽光発電システム ・蓄エネ:家庭用蓄電池(または電気自動車) ・省エネ:HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム) |
(1)創エネ:太陽光発電システム
太陽光発電システムは、屋根に設置した太陽光パネルが太陽の光を受けて発電する装置です。
太陽光発電システムの設置には太陽の光を浴びて発電するための太陽光パネル、発電した電気(DC)を家庭で使用できる電気(AC)に変換するパワーコンディショナ、太陽光パネルを設置するための架台、配線・設置工事費などの費用が掛かります。
一般的な費用相場は、新築住宅・既存住宅あわせた全体平均で約120万円程度といわれています。
自宅で作った電力は自宅で使うことができ、余分な分は売電することもできます。
(2)蓄エネ:蓄電池(住宅用蓄電池・EV車)
蓄電池は、太陽光発電などでつくった電気を貯めて必要な時に使えるようにする装置です。
発電した電気を無駄にすることなく有効活用でき、災害時や停電時も生活に必要な電力を確保できるなど、電気の自給自足をすることができます。
貯めておける電気の量が多いものほど高額になりますが、一般的に蓄電池の費用は本体と設置費用で90万~250万円が相場です。
また、近年では電気自動車(EV)を家庭用電源として活用できる「V2H(Vehicle to Home)」の仕組みにも注目が集まっています。
(3)省エネ:HEMS
HEMSは、家庭内の電力使用状況を見える化し、機器の自動制御によって省エネを図るシステムです。
電気の使用量をリアルタイムでモニタリングし、どの家電がどれだけ電力を消費しているかをグラフや数値で把握できるため、無駄な電気の使い方に気付きやすくなり、節電への意識が高まります。
また、人がいない部屋の照明の自動消灯や、来客時の玄関の灯りを自動点灯、帰宅時間に合わせてエアコンの起動などスマート家電と連携する機能も備えており、より効率よく使うことができるようになります。
HEMSの導入費用は、新築の場合(住宅分電盤込み)は約22万~26万円、リフォームの場合(住宅分電盤なし)は約11万~20万円が相場です。
発電・蓄電と合わせてHEMSを合わせて導入することで、家全体の電気の使い方を最適化し、光熱費削減やCO₂排出抑制などの省エネと快適性を両立することが可能になります。
3.スマートハウスのメリット

スマートハウスには、生活コストや安全性、暮らしの質を重視する方にうれしいメリットが多くあります。
| 【スマートハウスのメリット】 ・光熱費の削減ができる ・災害時・停電時の備えができる ・補助金・税などの優遇が受けられる ・IoT機器との接続により生活の利便性・快適性がアップする |
(1)光熱費の削減ができる
スマートハウスは太陽光発電や蓄電池、HEMSなどによりエネルギーの創出・貯蔵・管理に重点を置いた省エネ住宅であり、光熱費の削減が可能です。
太陽光発電システムにより日中に発電した電気を蓄電池に貯めて使用することで電力の自給自足を実現でき、電力会社への依存を減らすことができます。
特に電気代が高騰している今、エネルギーの自給自足による家計負担の軽減が大きな魅力です。
さらに、自宅で使う光熱費の削減だけでなく、余った電力を電力会社に売る(売電)ことによる収益も期待できます。
(2)災害時・停電時の備えができる
スマートハウスは、災害時にも非常用電力を確保できるという点で、大きな安心をもたらしてくれる住宅でもあります。
たとえば、地震や台風などの自然災害による停電の際も、太陽光発電システムが昼間に電気をつくり、蓄電池に電力を蓄えておくことで停電中にも電力を使うことができます。
特に、災害時の情報収集や安否確認に欠かせないスマートフォンやテレビ、食料確保に必要な冷蔵庫、照明など生活に必要な機能を確保できるのは大きなメリットです。
災害への備えが求められる今、自分たちの電力を自分たちで確保できるスマートハウスの価値や意義はさらに高まっています。
(3)補助金・税などの優遇が受けられる
スマートハウスは自治体や国の補助金の対象となることが多く、初期費用の負担を抑えて設置することができます。
また、スマートハウスやZEH(ゼッチ)として認定された住宅を新築または取得する場合には、住宅ローン減税や固定資産税の減額措置、贈与税の非課税枠の拡大(親からの住宅取得資金)など、さまざまな税制優遇措置が受けられ、長期的な税負担も抑えることが可能です。
(4)IoT機器との接続により生活の利便性・快適性がアップする
スマートハウスのHEMSとスマート家電、センサーなどIoT機器と連携させることで、快適性や利便性を高めつつエネルギー管理が行えるのも大きなメリットです。
たとえば、センサーで室温の変化を検知してエアコンを自動調整したり、照明や家電の電源を自動や音声でオン/オフするなどIoT機器によりさらに室内で便利に過ごせるようになります。
また、外出先からエアコンや給湯器の操作を行うなど外から家電や設備を操作できるようになることで、より便利でストレスの少ない生活を実現し、暮らしの質を大きく向上させることができます。
4.スマートハウスのデメリット
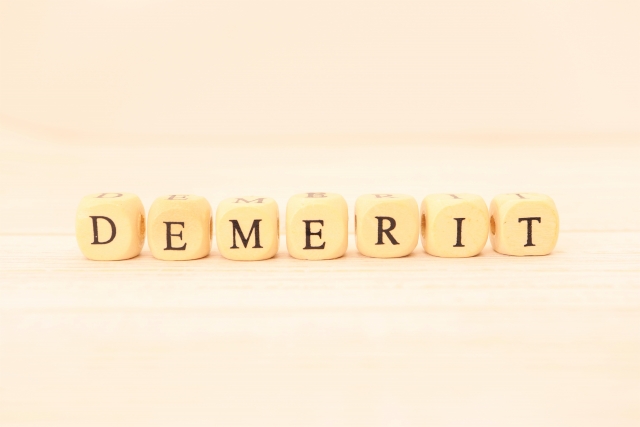
スマートハウスにはメリットも多いですがデメリットもあります。
導入を検討する際は、スマートハウスのデメリットをよく理解し、生活スタイル・優先事項に照らして判断することが重要です。
| 【スマートハウスのデメリット】 ・初期費用がかかる ・メンテナンスコストがかかる ・天候の影響を受けやすい(発電の場合) ・セキュリティのリスクがある |
(1)初期費用がかかる
太陽光発電、蓄電池は機器や関連設備なども含めた設置費用が高額なため、初期費用が高くなる傾向があり、さらにHEMS対応家電に買い替える場合はそのコストもかかります。
戸建て住宅への太陽光発電システム設置費用相場は新築で26.1万円/kW、既築で28.1万円/kW、家庭用蓄電池の設置にかかる費用の相場は蓄電池本体のみで14.9万〜183.4万円、工事費を含む費用は48.4万〜216.1万円とかなり高額になります。
また、「エネルギーの見える化」や「スマート制御による省エネ」機能が付いたHEMS対応家電は、一般的に非対応の家電と比べてやや高価になる傾向があります。
現在、自治体や国で上記の設備を搭載した新築・リフォーム住宅に補助金が出ることも多いため、上手に補助金を利用するのがおすすめです。
(2)メンテナンスコストがかかる
太陽光発電システムや蓄電池を導入する際には、初期費用だけでなく定期的なメンテナンスコストも考慮する必要があります。
10kW未満の一般家庭用では、10kW以上の太陽光発電設備のように法律(改正FIT法)による4年に1回以上の定期点検の義務化はされていませんが、安全で長期間の使用のために定期点検やメンテナンスが推奨されています。
定期的なパネルの清掃や点検費用、10〜15年に一度のパワーコンディショナの交換費用(30万〜40万円程度)を含む年間の維持費はおおよそ5,800円/kW程度が目安です。
また、蓄電池についても年1回程度の点検が推奨され、その都度費用が発生します。
太陽光発電システムや蓄電池の寿命もあるため、長期使用には点検だけでなく将来的な交換費用も見込んでおく必要があります。
(3)天候の影響を受けやすい(発電の場合)
スマートハウスには、天気が悪い日や冬季など日照時間が短いと発電量が大きく減少するなど、天候の影響を受けやすいというデメリットがあります。
停電時でも太陽光と蓄電池で必要な電力をまかなえることがスマートハウスの強みですが、それも天候次第です。
環境・タイミングによっては思ったように発電できないこともあります。
(4)セキュリティのリスクがある
スマートハウスに家庭内の設備や家電をインターネットとつなぐIoTを導入している場合、ハッキングや不正アクセスなどのリスクがあります。
エコで省エネと環境にも家計にも優しいスマートハウスですが、十分な安全対策をとっておかないと乗っ取りや通信の盗聴・傍受などのプライバシー侵害、個人情報の漏洩などの危険にさらされる可能性があります。
安全に暮らすには次のセキュリティ対策をとることをおすすめします。
| 【おすすめのセキュリティ対策】 ・信頼できるメーカーの製品選び ・複雑で強力なパスワード設定 ・2段階認証の利用 ・定期的なアップデート ・ネットワークの分離(スマート家電専用のWi-Fiを設け、他の機器と分ける) |
さらに強力なセキュリティ対策を施すなら、インターネット上での通信を暗号化して安全に利用できる技術であるVPN(Virtual Private Network)の利用もおすすめです。
スマートハウスもFINDにご相談を
発電・蓄電・節電の3つを自宅で行うスマートホームは、エコで経済的であるだけでなく、非常時にも安心できる、電力の自給自足を実現する理想的な住まいです。
導入には高額な費用が必要ですが、国や自治体の補助金を利用することで自己負担をおさえて導入することが可能です。
FINDは神奈川県川崎市に本社を構える、リノベーション、リフォーム、不動産売買仲介、空間デザイン、ファイナンシャルプランニング、ホームインスペクションまで行うリノベーション会社です。
FINDでは、その家で暮らすご家族が毎日を笑顔で心地よく過ごせるように、安全性や生活スタイル、動線にも配慮した、使いやすくて便利なリノベーションを提案しており、スマートハウスのご相談も承っております。
経験豊富なプランナーがチームとなって理想どおりの家作りを行っていくため、安心してお任せください。

ライフディレクション事業部 設計チーム / 一級建築士 / 既存住宅状況調査技術者