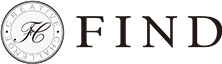COLUMNコラム
- 2025.05.01
- 住宅リノベーション
リノベーションで耐震補強!費用相場や工事をする際のポイントを解説

「リノベーションをする際に耐震補強も行なったほうがいい?」
「耐震補強の内容や費用相場を知りたい」
このような悩みをお持ちではありませんか?
家の安全性は、そこで暮らす家族の命を守るために重要です。
本記事では、リノベーションと同時に行いたい耐震補強について、同時進行するメリットや耐震補強の工事内容・費用相場、流れや注意点まで詳しく解説します。
大切な家族が安心して暮らせるように、リノベーションと耐震補強を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
目次
1.リノベーションで耐震補強もするべきなのか?

リノベーションを行う際は、暮らしやすさだけでなく家の安全性を高めることも大切です。
そのため、リノベーションと同時に耐震補強を行うことをおすすめします。
なぜリノベーション時に耐震補強をすべきなのかその根拠やメリットを解説します。
| ・近年の地震リスクと住まいへの不安 ・耐震補強をするメリット ・リノベーション時に耐震補強を同時に行うべき理由 |
(1)近年の地震リスクと住まいへの不安
日本では近い将来、大地震が予測されており、多くの人が防災グッズを準備して対策をしています。
しかし、どれだけ防災グッズを揃えても、もし自宅が倒壊してしまったら、元も子もありません。
安全な住環境を確保するために、建物自体の耐震対策が非常に重要です。
実際、2021年3月に発表された日本木造住宅耐震補強事業者協同組合の調査によると、診断した27,929棟のうち9割超が現行の耐震基準を満たしていないという結果が出ています。
また、総務省消防庁の資料では、最大震度7以上を観測した東日本大震災で被害を受けた住宅の多くが旧耐震基準で建てられた建物であることが分かっています。
いつ来るかわからない地震に備えるため、自宅の耐震補強はできるだけ早く取り組みたい問題の1つであるのは間違いありません。
(出典:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 木耐協調査データ 2021年3月発表 )
(出典:消防庁消防研究センター 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)災害情報 )
(2)耐震補強をするメリット
地震に備えて自宅に耐震補強をすることには次のメリットがあります。
| ・地震による倒壊リスクを大幅に軽減できる ・地震被害による修繕費用を抑えられる ・安心して長く住み続けられる ・建物の資産価値が向上する |
強度面で不安のある自宅に耐震補強を施すことで、家族が安心して暮らせる日々を手に入れられることは何よりも大きなメリットと言えるでしょう。
(3)リノベーション時に耐震補強を同時に行うべき理由
耐震補強には多くのメリットがありますが、リノベーションと同時に行うべき理由は以下の通りです。
| ・内装や間取りの工事と一緒に構造部分の補強がしやすい ・壁や床を剥がすタイミングが共通しており、工事コストと工期を抑えられる ・後から耐震工事を行うより効率的で費用対効果が高い ・同時に補助金・減税の申請対象となる場合もある |
リノベーションと別々に耐震補強工事を行うとコストや時間が二重にかかりますが、両方を同時に実施することで効率よく進められます。
また、補助金の対象や減税の対象となることも多いので経済的な負担軽減も可能です。
リノベーションを行う際は同時に耐震補強も行い、快適さと安全性を高めるのがおすすめです。
2.リノベーションでの耐震補強工事の費用相場と工事内容

次に、耐震補強工事にどれくらいの費用が掛かるのかをみてみましょう。
耐震補強工事の費用は工事内容や住宅によってかなり差が生じますが、150万円前後が相場とされています。
| 平均施工金額 ・旧耐震基準住宅 189万2,208円 ・新耐震基準住宅 152万3,430円 |
(出典:日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 木耐協調査データ 2021年3月発表)
新耐震基準で作られた住宅よりも、旧耐震基準で作られた住宅は補強箇所も多くなるため、費用が高額になる傾向があります。
ここからは一般的な施工内容について部分別に解説していきます。
| ・基礎の耐震補強 ・壁の耐震補強 ・柱の耐震補強 ・屋根の耐震補強 |
(1)基礎の耐震補強
建物の土台を支える基礎部分の補修・補強を行います。
主な施工内容は以下のとおりです。
| 施工内容 ・湿気やシロアリ、地盤沈下等で傷んだ土台の差し替え ・コンクリート基礎に鉄筋を入れて補強 ・コンクリート基礎のひび割れの補修(樹脂注入) ・アンカーボルトの設置・増設 |
ひび割れの補修やアンカーボルトの設置・増設などの工事は、比較的短期かつ安価に実施できますが、広範囲にわたる土台の差し替え工事などは大がかりとなり、相応の費用と時間がかかります。
(2)壁部分の耐震補強
家の強度を面で高める耐震補強です。
主な施工内容は以下のとおりです。
| 施工内容 ・壁の補強(配置の見直し、壁自体の補強) ・耐震金物を取り付け建物の強度を補強する |
壁の耐震補強は筋交いや強度の高い壁材(耐力壁)で壁の強度を上げたり、耐力壁をバランスよく配置する工事となります。
また、柱や土台との接合部を補強金具で固定するなどの工事も行います。
(3)柱部分の耐震補強
建物の骨組みを強化して柱部分の強度を高める工事です。
主な施工内容は以下のとおりです。
| 施工内容 ・柱の強化・取り換え ・耐震金物を取り付けて強度を補強する |
補強金具で固定する工事が一般的ですが、シロアリや湿気などで柱が老朽化し、基礎や柱周りの梁を含む大規模な工事になった場合は費用も高額になります。
(4)屋根部分の耐震補強
屋根部分を軽量化する工事です。
主な施工内容は以下のとおりです。
| 施工内容 ・屋根の素材を軽い素材(軽量瓦・金属屋根・化粧スレート屋根)などに変更する |
屋根は重さがあるため、地震時に揺れによって落下や変形が起こることがあります。
屋根の耐震補強を行うことで、屋根が建物の構造としっかりと連携し、揺れを分散させることができます。
3.耐震補強工事の流れ

次に、耐震補強工事を行う際の流れについて見てみましょう。
| 1.耐震診断を依頼する 2.耐震診断の結果を踏まえ、補強設計を行う 3.補強設計に基づき、耐震補強工事を行う 4.工事完了後、完了報告書と耐震審査を行い、補助金を受領する(補助金を利用する場合) |
耐震補強の流れは、まず専門の耐震診断士に依頼して自宅の耐震診断を受けることから始まります。
この診断結果をもとに、どのような補強が必要かを決めるための補強設計が行われます。
設計が決まったら、実際に耐震補強工事が進められ、基礎や壁、柱、屋根など、家の重要な部分を強化します。
工事が完了した後には、完了報告書が作成され、耐震審査が行われます。
この報告書を提出すれば、補助金を利用できる場合があり、経済的な負担を軽減する手助けになります。
4.リノベーション時に耐震補強を同時に行う際のポイント

ここでは、耐震補強をスムーズに進めるためのポイントを紹介します。
| ・住宅診断を事前に実施する ・最新の工法を活用する ・補助金や税制優遇を活用する |
(1)住宅診断を事前に実施する
住宅診断(ホームインスペクション)とは、住宅診断士(ホームインスペクター)が専用の計測機器等を用いて、家の傾きやヒビなどを詳細に確認・診断するものです。
目視や機器で確認できる範囲で建物やコンディションを把握・推測することで、より効率よくプランを考案することができます。
(2)最新の工法を活用する
耐震補強工事というと大がかりな工事をイメージしてしまいますが、最近では簡易に耐震補強ができる工法も登場しています。
例えば、SRF工法を使えば、基礎や合板の上に高弾性ベルトを弾性接着剤で貼るだけで耐震補強ができます。
この方法は工事が簡単で、費用を抑えながら短期間で補強を行うことができます。
リノベーションと同時に耐震補強を行う際は、最新の工法を導入している会社を選ぶことで費用をさらに抑えることができます。
(3)補助金や税制優遇を活用する
耐震補強については、自治体の補助金、国の耐震リフォームにおける減税制度を受けられることも多いです。
自治体のHPや窓口だけでなく、リノベーション会社でも利用できる補助金や税制優遇について教えてくれることも多いので相談しましょう。
5.耐震補強の前に押さえておきたい用語解説
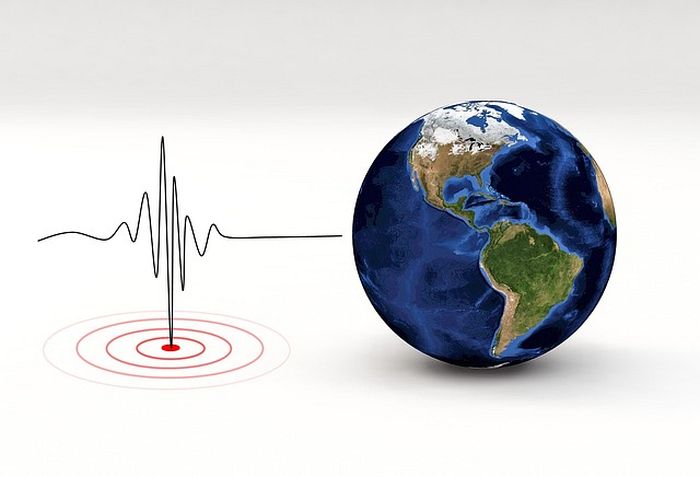
最後に、耐震補強をする前に理解しておきたい用語を解説します。
| ・旧耐震基準と新耐震基準 ・耐震等級 ・耐震・制震・免震について |
(1)旧耐震基準と新耐震基準
耐震補強をする上で重要となるのが耐震基準です。
1978年の宮城県沖地震で多くの家屋が倒壊したことから耐震規定が厳格され、1981年6月1日以降は震度6以上を想定した基準に変更されました。
| 旧耐震基準 | 新耐震基準 | |
| 時期 | 1950年から1981年の抜本的改正以前 | 1981年6月1日施行(昭和56年改正) |
| 対象となる建物 | 1981年5月31日以前の建物 | 1981年6月1日以降に建築確認済の建物 |
| 耐震レベル | 震度5程度 | 震度6〜7 |
震度6以上の地震を想定していない旧耐震基準で建てられた住宅は近年の地震でも大きな被害を受けています。
(2)耐震等級
耐震等級とは建物の強度を表す指標であり、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて0~3まで4つの段階で表されます。
| 等級 | 強度のレベル |
| 耐震等級0 | 現在の耐震基準を満たしていない建物 |
| 耐震等級1 | 現行の建築基準法による耐震基準を満たしている住宅 |
| 耐震等級2 | 耐震等級1の1.25倍の耐震性を備えた住宅 (病院や学校等避難所となる建物の耐震性 |
| 耐震等級3 | 耐震等級1の1.5倍の耐震性を備えた住宅 (消防署や警察署等の防災の拠点となる建物の耐震性) |
耐震等級1は、現行の建築基準法による耐震基準を満たしていることが条件となります。
等級数が大きいほど耐震性が高い住宅となり、最高の耐震等級3であれば震度6強~7の大地震時においても大きく損傷することなく軽微な補修のみで耐えられるレベルの耐震性を持つ住宅となります。
耐震等級は耐震補強工事を実施することで上げることが可能です。
耐震等級を上げることで安心を得られるだけでなく、地震保険料の割引や長期優良住宅の認定により減税措置や補助金を取得できるなどのメリットもあります。
(3)耐震・制震・免震について
「耐震」「制震」「免震」は、地震対策として建物に取り入れられる技術で、それぞれ地震の揺れに対するアプローチが異なります。
| 耐震 | 耐震は、建物自体を頑丈にして、地震の揺れに耐えることを目的とした構造です。柱・梁・壁などの強度を高めたり、耐震壁や筋交いを取り入れたりして、建物の倒壊や損傷を防ぎます。 |
| 制震 | 制震は、建物の中に「制震装置(ダンパー)」を組み込み、揺れを吸収・減衰することで建物へのダメージを軽減します。 |
| 免震 | 免震は、建物と地面の間に免震装置(ゴムやベアリングなど)を設置し、地震の揺れそのものを建物に伝えないようにする技術です。 |
制震・免震も地震に備える有益な工事ですが、耐震工事よりも大がかりとなり、時間・コストがかかってしまうというデメリットがあります。
リノベーションを行う際に耐震工事も行うことが時間・コストをおさえて家の安全性を高める最善の方法といえるでしょう。
FINDで安心の耐震補強リノベーションを
FINDは神奈川県川崎市に本社を構える、リノベーション、リフォーム、不動産売買仲介、空間デザイン、ファイナンシャルプランニング、ホームインスペクションまで行うリノベーション会社です。
FINDでは、その家に暮らす人が快適に過ごせるように生活スタイルや動線も踏まえて使いやすくて便利なリノベーションを提案しています。
さらに、住まいの安全性についても十分に考慮し、ご家族が安心して暮らせるよう住まいの耐震補強工事についても対応しています。
経験豊富なプランナーがチームとなって人が満足できる家作りを行っていくため、安心してお任せください。
見積もりは無料で承っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ライフディレクション事業部 設計チーム / 一級建築士 / 既存住宅状況調査技術者